倭文神社 伯耆國の由来を説き明かす

倭文神社(しどりじんじゃ)は鳥取県東伯郡に鎮座するご聖域。
ご祭神は、経津主神や武甕槌神すらも超える最強の武神・建葉槌命!
そんな建葉槌命が鎮まる『伯耆國の由来』を説き明かして行きたいと思います。
なお、倭文神社のご紹介記事は下記リンクをご参照下さい♪
幸運をもたらす伯耆國

今回のテーマは伯耆國の由来を探ること。
そこで、出番となるのが風土記です。
早速、伯耆國風土記を見てみると…
八頭之蛇が襲ってきたため、稲田姫は山中に逃げた。
その時、母が来るのが遅かったので、稲田姫は「母來(ははき)」と言った。
故に母來國(ははきのくに)と名付けられ、後に伯耆國(ほうきのくに)と改められた。
八頭之蛇(やまたのおろち)から逃げる時、母が来るのが遅かったので、稲田姫は…
お母さん、早く来て!母来!と叫んだ。
この母來(ははき)がそのまま国名となり、後に伯耆(ほうき)となったそうです。
あっさり解決してしまいましたね。
最強の武神・建葉槌命

そんな伯耆國一ノ宮の倭文神社に鎮まるのが建葉槌命(たけはづち)
日本書紀によると…
大國主命(おおくにぬし)は国譲りに従った。経津主神と武甕槌神は、諸々の従わない神たちを皆平げた。
従わないのは、星の神である香香背男(かかせお)だけとなった。
そこで建葉槌命(たけはつち)を遣わして、屈服させた。
大國主命は『出雲の国譲り』に従うものの、多くの神々は言うことを聞きません。
そこで派遣されたのが、最強武神と謳われる経津主神(香取神宮)と武甕槌神(鹿島神宮)
経津主神と武甕槌神は反乱軍を鎮圧するも、香香背男だけには歯が立ちませんでした。
そこで登場するのが、建葉槌命。

経津主神や武甕槌神が全く歯が立たなかった香香背男を、建葉槌命は屈服させます。
つまり…
建葉槌命は、経津主神や武甕槌神すら超える最強武神なのです。
そして、そんな最強武神が鎮まる國こそが…
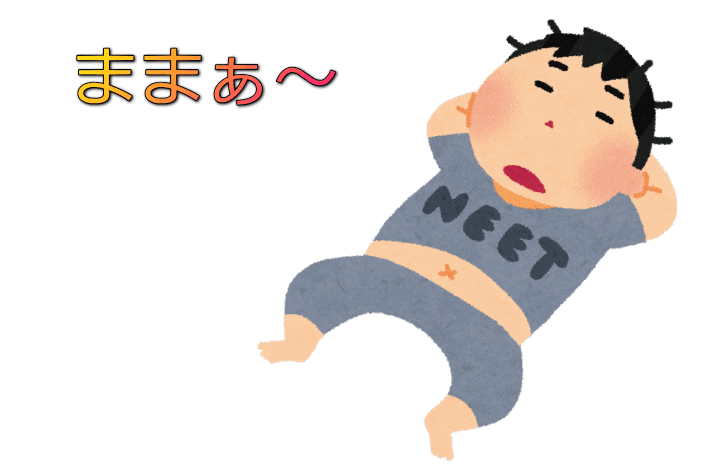
『ママ、かも~ん!(母來國:ははき)』
。
。。
。。。
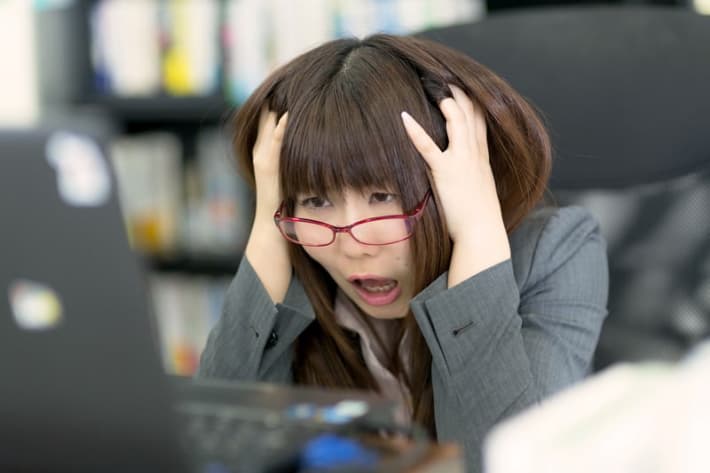
何か違う…
東日流外三郡誌・荒脛巾

風土記による『母来』では納得出来ません。そこで探求を続けます。
まず、日本語にとって字は当て字に過ぎず、音こそが全てです。
その為、母来という字に惑わされることなく『ははき』という音を探る必要があります。
そこで『ははき』と聞いて思いつくのが…

荒脛巾(あらはばき)!
東日流外三郡誌によると『荒脛巾』は、初代神武天皇の宿敵『長脛彦』のこと。
つまり『ははき』とは『長脛彦』のことで、神武東征の激戦地も鳥取県だったのです!
…と言いたいところですが…

東日流外三郡誌は昭和に創作された偽書で、信憑性はゼロ。
そもそも脛巾は『はばき』とは読みません。
漢字に惑わされ『脛』から長脛彦を連想したのでしょうが…
東日流外三郡誌は、爪の甘い創作偽書なので『ははき』=『長脛彦』の線は消えました。
日本書紀・天羽羽斬

では『ははき』とは一体何なのでしょう?
そこで日本書紀の出番です。
信憑性の疑わしい古伝を持ち出さなくても、日本書紀にちゃんと書いてありました。
その内容は…

素戔鳴尊は出雲の國の簸の川の上流にある鳥上の山に着いた。
すると、そこには人を呑む大蛇がいた。
素戔嗚尊は天蠅斫剣(あまのははきりのつるぎ)をもって、その大蛇を斬られた。
素戔嗚尊が出雲に天下った時に、八岐大蛇と激突します。
その際、八岐大蛇を斬った剣が『ははきり』
では『ははきり』の意味は何かというと…
古来、大蛇のことを羽々(はは)と言う。
天羽羽斬と呼ぶ故は大蛇(はは)を斬ったからである。
八岐大蛇という大蛇(はは)を斬ったからこそ天羽羽斬と呼ばれる。
つまり『はは』とは大蛇のこと。
それでは『き』とは何かというと…
次に成りし神の名、
男:伊邪那岐(いざなき)
女:伊邪那美(いざなみ)
古き言葉において『き』とは男性のこと。
つまり『伯耆』とは…

大蛇男という意味です!
忌むべき幸運の大蛇王

風土記にある、『ママ、かも~ん!!』では國名としては情けなさ過ぎます。
だからと言って『大蛇男』という忌まわしき國名も不適切。
しかし、伯耆の由来は『大蛇男』

かつて、日本は海を拠点とする海洋民族と、森で暮らす森の民が住まう国でした。
しかし、農耕民族である大和朝廷が、国内を統一します。
その大和朝廷にとって、田畑を食い荒らし、死をもたらすのが、蛇という忌むべき存在。

しかし、海洋民族にとって、蛇は水辺に住む水の神であり、蛇は豊穣や繁栄の象徴。
さらに、脱皮を繰り返すことから、古代より蛇は再生の象徴。
そんな蛇を信じる海洋民族が住んでいたのが鳥取県。
そこで、大和朝廷は鳥取県を征服した際に、海洋民族にとって喜ぶべき名を与えます。

それが…
幸運をもたらす大蛇王。
つまり、羽羽岐(ははき)

大和朝廷は、海洋民族を持ち上げながらも、忌むべき名で侮蔑する。
大和朝廷は、プライドをくすぐりながらも、事実上は支配する。
伯耆に限らず、全国で起きたことです。

羽羽岐(ははき)とは、固有名詞ではなく、将軍、国王などの称号に過ぎません。
従って、日本には多くの羽羽岐(ははき)がいました。
しかし、これをあえて国名にしたこと。
さらに、復活しないよう、最強の武神である建葉槌命で羽羽岐を封じ込めたこと。

このことを考えると『伯耆國』というのは、ものすごく重要な場所なのかも知れません。
倭文神社の写真ギャラリー
↓クリックで拡大、左右で移動。
倭文神社へのアクセス
倭文神社
鳥取県東伯郡湯梨浜町宮内754
山陰本線・松崎駅バス停→藤津入口停留所。
徒歩20分ほど。
















