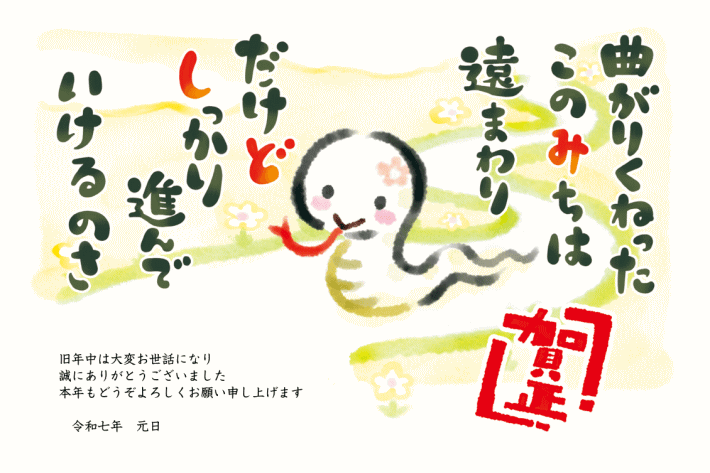古史古伝~ウソかマコトか偽書の真実
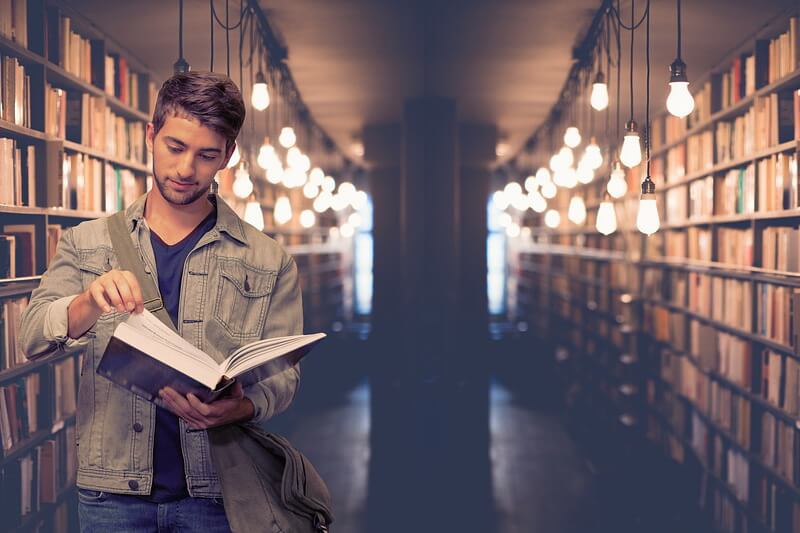
古事記・日本書紀は、最古の歴史書である。
だが、古事記・日本書紀は捏造された偽書という疑惑が持たれている。
そして、それに呼応するように…
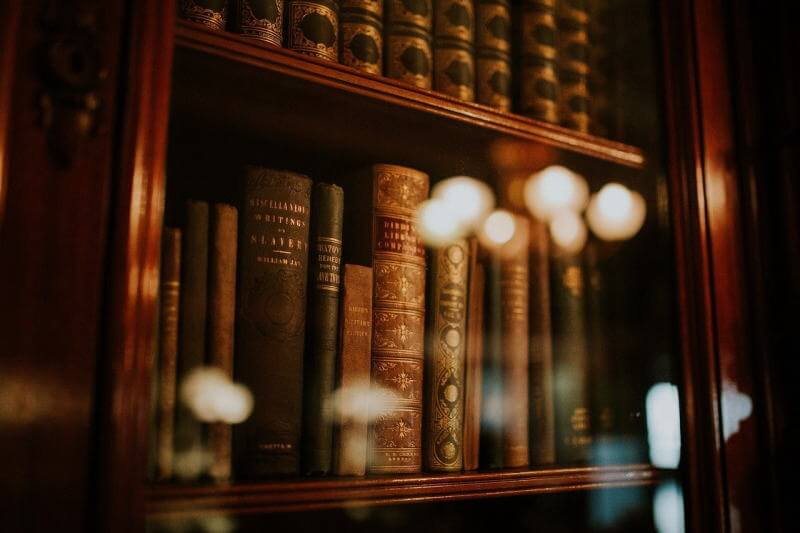
竹内文書、ホツマツタエ、宮下文書。
出雲王朝の興亡を描いた富王家伝承。
本当の歴史を描いた史書が発表されてきた。
だが、これらの史書、いわゆる古史古伝は…
これを前提としている。
では、はたして古事記・日本書紀は、本当に真実を描いていないのか?
それを解き明かしていこう。
繰り返される歴史

【日向神話】
彦火火出見(山幸彦)は天孫・瓊瓊杵の子で、末子として産まれた。
だが、自分自身の不注意で兄の逆鱗に触れ、祖国を追われるハメとなる。
しかし、異國の海宮で「海神・綿津見」という強力な後ろ盾を得て帰国。
綿津見の力を得た彦火火出見は、兄を征し、日向の英雄となった。

【出雲神話】
一方、出雲の大國主命も八百万神の一柱で、末子として産まれた。
そして、こちらも兄の逆鱗に触れてしまい、祖国を追われるハメとなる。
しかし、異國の根國で「英雄スサノオ」という強力な後ろ盾を得て、出雲に帰国。
スサノオの力を得た大國主命は、兄を征し、出雲の英雄となった。

どうやら、時代や場所は違えども…
末子が兄を征する。
これが古代のセオリーらしい。
消息を絶つ姫

【日向神話】
彦火火出見は、異國の地で豊玉姫と結ばれ、子供が生まれた。
しかし、豊玉姫は子供が生まれると、スグに子供を置いて去ってしまう…
乃以草裹兒棄之海邊閉海途而徑去矣
草で子を包み、海辺に棄てて、海路を閉じてすぐに帰ってしまった。
その後、豊玉姫の消息不明である。

【出雲神話】
一方、大國主命も、異国で八上姫と結ばれ、子供が生まれる。
しかし、本妻の須世理姫を恐れて、八上姫は子供を置いて去ってしまう…
其八上比賣者、雖率來、畏其嫡妻須世理毘賣而、其所生子者、刺挾木俣而返。
本妻である須勢理毘売を恐れ、生んだ子は木の股に挿し挟み、因幡へ帰った。
その後、八上の消息不明である。
どうやら、時代や場所は違えども…
これが古代のセオリーらしい。
叔母との結婚

【日向神話】
母に捨てられた鸕鶿草葺不合は、母親の妹、すなわち叔母に育てられる。
その後、自分を育ててくれた叔母と結婚し、4人の子供が生まれた。
その4人の子供の中でも末子は別格であり、祖父の兄、饒速日を征し、王となった。
いわゆる、神武天皇である。

【失史八代】
神武には、2人の妻と、5人の子がいた。
その中でも、末子は別格で、異母兄を征し、二代天皇となる。
その後、実母の妹、すなわち叔母と結婚。
これが綏靖天皇である。

どうやら、時代や場所は違えども…
叔母(母の妹)と結婚する。
これが古代のセオリーらしい。
産屋に火をつける

【日向神話】
天孫・瓊瓊杵は、日向で木花開耶姫と会い、子供が生まれた。
だが、瓊瓊杵は認知しようとしない。
この不誠実な対応に木花開耶姫は怒り狂い、産屋に火を付け出産する。
木花開耶姫、甚以慙恨、乃作無戸室而誓之曰「吾所娠、是若他神之子者、必不幸矣。是實天孫之子者、必當全生」則入其室中、以火焚室。
この時に生まれたのが彦火火出見である。

【19代允恭天皇】
19代允恭天皇には、長年苦難を支え続けた忍坂大中姫という皇后がいた。
だが、忍坂大中姫の支援を忘れ、浮気三昧。
この不誠実な対応に忍坂大中姫は怒り狂い、産屋に火を付け出産する。
皇后聞之恨曰「妾初自結髮、陪於後宮、既經多年。甚哉天皇也、今妾産之死生相半。何故、當今夕必幸藤原。」乃自出之燒産殿而將死
どうやら、時代や場所は違えども、古代では炎を放って出産する。
これがセオリー…

そんな訳がない。
古事記・日本書紀の製作過程

古墳時代の5世紀。倭の五王の時代
中国で言えば宋の時代。
国内を二分するある事件が起きた。
この勝者の【後継】が、実在が確実視される29代・欽明天皇である。

そして『ある事件』の勝者は、勝者の視点で歴史を残した。これをAとする。
同時に『ある事件』の敗者も、敗者の視点で歴史を残した。これをBとする。
敗者の伝承 B
この時点で『伝承が2つ』存在する。

さらに、これらを支えた複数の豪族がいた。
その為、勝者側の豪族は、勝者側の視点で、勝者の伝承をそれぞれ残した。
同時に、敗者側の豪族も、敗者側の視点で、敗者の伝承をそれぞれ残した。
すると…
敗者の伝承 B、B1、B2、B3…
事件は1つだけだが、複数の伝承が存在することとなる。

40代・天武天皇の御代。
複数の伝承をまとめて、国書を編纂するよう命が下る。
古事記・日本書紀である。
ところが、編纂の過程で問題が起きた。
それは…

各豪族の伝承は、自分達にとって都合の良い内容だったこと。
同じ事件なのに、整合性が取れないこと。
それを確認しようとも、古代の出来事を知る証人などいなかったこと。

その結果…
後勘校者、知之也。
訳が分からないので、後世の研究者たちに任すことにした…
編纂者たちは匙を投げてしまった。
だが、天皇からの絶対命令。
口が裂けても出来なかったとは言えない。
そこで編纂者は5世紀頃の出来事の事件を、時間をズラして何度も繰り返すことにした。

結果、神武帝以来『万世一系』の書を天皇に献上することは出来た。
だが、登場人物も、時代も、微妙に違うが、同じ話を繰り返す代物。
既述の末子、育児放棄、叔母、出産なども、その1例に過ぎない。
これが古事記・日本書紀の実態である。
大國主命の正体

古事記・日本書紀は神世からの書ではなく、同一時代の繰り返し書である。
出雲神話もしかり。
大國主命も神代にいた神ではなく…
そして、現代から過去、過去から神代へと、何度も登場する人物である。
ただし、オリジナルは独りである。
これは他の神々にも、他の天皇にも言える。
古事記・日本書紀の真偽

古事記・日本書紀に偽書疑惑が生じるのは、時系列に問題があるからである。
しかし、時系列と、繰り返しの問題のみで、伝承の大枠に問題はない。
この点において、古事記・日本書紀は偽書ではない。
古史古伝はどうか?

では、竹内文書、ホツマツタエ、宮下文書、富王家伝承はどうか?
書によって微妙の差異はあるが『時系列』は古事記・日本書紀に沿っている。
だが、古事記・日本書紀の時系列を正とした時点で、偽書だと言わざるを得ない。
ようは、古事記・日本書紀をたたき台とした二次創作本でしかないのである。
まとめ

文字のない時代。
歴史は口伝によって伝承されてきた。
しかし、神代の事は創作が出来たとしても、実在したヒミコの実話は伝承出来ない。
何故なら、口伝では400年・500年も経てば忘れ去れてしまうからだ。

古事記・日本書紀もしかり。
29代・欽明天皇以降のことは明記出来ても、それ以前は時代が遡るほど曖昧となる。
まして、400年・500年も前の事となると、記憶すらなくなってしまう。
文章化出来るのは100~200年前が限界だ。
事実、多くの神々も、口頭伝承が残っていた100~200年前を神話化したものである。

当サイトにおいて、最もアクセスが多いのはニギハヤヒの正体である。
2025年、今回の視点をもとに…
これを記載する。